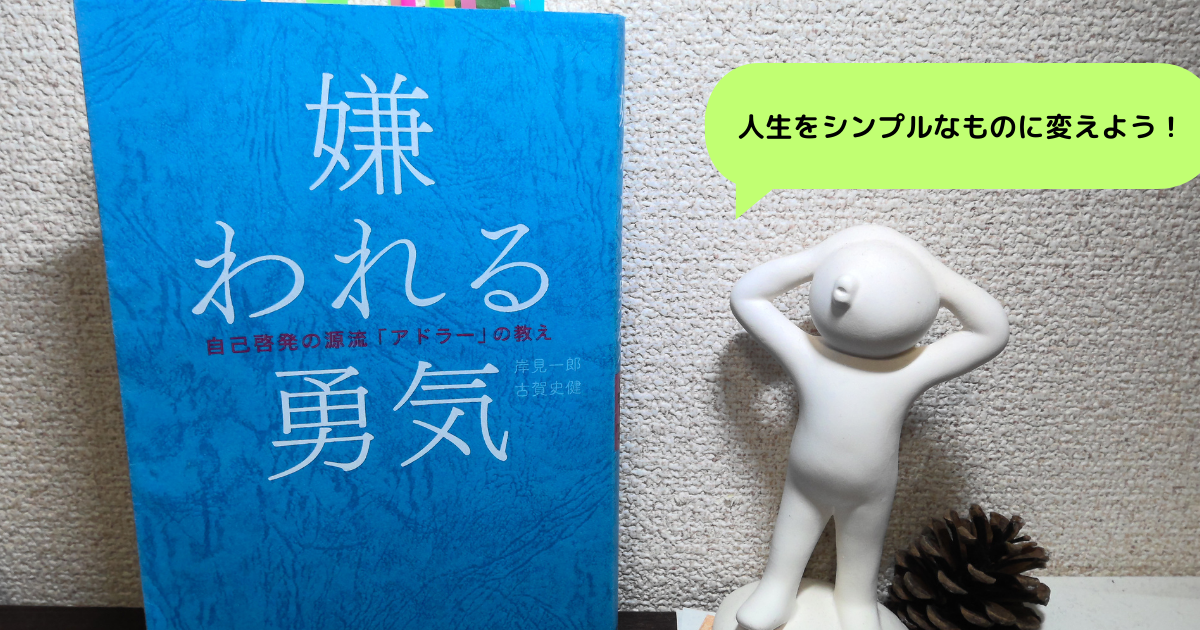こんにちは、haruです。
アドラー心理学の要点をまとめたこの本、『嫌われる勇気』には、人生を生きる上でのエッセンスがたっぷりと詰まっています。
これを読んだ高校時代の僕は、なんと世界はシンプルなんだ!と感動した記憶があります。それを皆さんにも感じてもらいたいと思い、要約を書くことにしました。
『嫌われる勇気』は、青年と哲人の会話形式は進んでいきます。
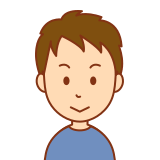
人って変われるの?
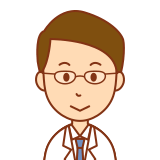
変われるし、みんな幸福になれます
こんな感じ。
さて、この本の内容を全て理解するのは一筋縄ではありません。ゆっくりと咀嚼しながら読んでいただきたいです。
長い夜になります。熱いコーヒーでも用意して読んでください。(哲人風)
第一夜 過去の原因ではなく、今の目的を考える
原因論と目的論の違い
突然ですが皆さん、今日はどうしても学校に行きたくないなっていう日、ありますよね。
例えば、授業中毎回先生に当てられて、うまく答えられない日が続き、明日も当てられるかもしれないから不安で学校に行きたくない。という場合を考えてみましょう。
この場合、原因論的立場から考えると、
「また先生に当てられないか不安だから、学校に行きたくない」ということになります。
それに対して、アドラー心理学の立場はこうです。
「学校に行きたくないから、不安という感情を作り出している」
理解できました?もう一度言います。
「学校に行きたくないから、不安という感情を作り出している」
これ、すごく突飛な言葉に思えるのですが、これを理解することがアドラー心理学を理解する最初の一歩です。
感情さえも目的論で考えることができます。
例えば、誰かに対して腹を立て怒鳴った時は、
「怒鳴るという目的が先にあり、その手段として怒りの感情を捏造した」と言えます。
そして、
もし物事を目的論的立場で見ることができた時、そこにはトラウマは存在しません。なぜなら、目的論で物事を考えた時、過去の出来事が今に影響を与えていないということになるからです。
アドラーはこういいます。
大切なのは何が与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである。
人は常に「変わらない」という決心をしている。
アドラー心理学では、性格や気質のことをライフスタイルという言葉で説明します。
ライフスタイルは、自ら選べるものだというのがアドラーの主張です。つまり、「不幸でいること」「ネガティブな性格であること」などを選んだあなたでも、「幸せになること」「ポジティブな性格であること」を選ぶことができるというわけです。
では、ライフスタイルは自ら選び取ることができるものなのに、多くの人が変わることができずにいるのはなぜでしょう?
それは、自分のライフスタイルを変えないでおこうと決心しているからです。
ライフスタイルを変えるとき、人は勇気を試されます。今のままのライフスタイルに慣れているので、人は変わらずにいようと思ってしまうのです。
具体的にどのようにライフスタイルを選び取るのかは、第二夜で言及されています。
僕の心に響いた文章があるので、引用します。これを読んで共感される方もいるのではないでしょうか。
哲人「私の若い友人に、小説家になることを夢見ながら、なかなか作品を書きあげられない人がいます。彼によると、仕事が忙しくて小説を書く時間もままならない、だから書き上げられないし、賞の応募に至らないのだそうです。しかし、はたしてそうでしょうか。実際のところは、応募しないことによって”やればできる”という可能性を残しておきたいのです。おそらく彼は、あと5年10年もすれば”もう若くないから”と別の言い訳を使い始めるでしょう。
『嫌われる勇気』p55 岸見一郎、古賀史健
第二夜 すべての悩みは対人関係
自分のことが嫌いなのは、対人関係を避けるため
自分の短所ばかりに目がいって、自分のことを好きになれないという人、いると思います。

僕も自分の良くないところばかりに目がいきます
なぜ自分のことが嫌いなのかを突き詰めて考えると、それは対人関係を避けるため、ということになります。
目的論で考えると、「他者との関係の中で傷つかないために、自分の短所を見つけて対人関係に踏み出せない人間になる」ということを選択しているということです。
劣等感と劣等コンプレックス
今、劣等感を感じていることありますか?「身長が低い」「目が一重で鋭い」など、挙げればきりがないかもしれません。
しかし、これらはすべて他人と比較した中で生まれる劣等感です。身長が低い人は、他の人よりも他人に安心感を与えるかもしれませんし、目が一重の人はクールな印象を与えるかもしれません。
ここで大事なのは、われわれを苦しめる劣等感は「客観的な事実」ではなく、「主観的な解釈」であるという点です。
そして主観は、自分の手で選択可能です。短所とみるか長所とみるかは自分次第ということです。
ところで、劣等感を抱くこと自体は悪いことではありません。「私は学歴が低いから、他の人より努力しよう」と決心するなら、むしろ望ましいことです。しかし、「私は学歴が低いから、成功できない」などと自らの劣等感を言い訳に使い始めるのはよくないです。このことを劣等コンプレックスと言います。
そして、哲人はこういいます。
哲人 「健全な劣等感とは、他者との比較の中で生まれるのではなく、”理想の自分”との比較から生まれるものです」
『嫌われる勇気』p55 岸見一郎、古賀史健
他者と比較する必要はないのです。
すべての悩みは対人関係である
ここまで劣等感の話をしてきて気づいた方もいるかもしれませんが、劣等感で悩んでいる人は、他者との比較の中で悩んでいるのです。つまり、他者がいなければ劣等感を感じることもないということになります。
アドラーは「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」といいます。
三つの人生のタスク
そこでアドラーは対人関係を次の三つに分け、これをまとめて人生のタスクといいます。
- 仕事のタスク
- 交友のタスク
- 愛のタスク
個人的にここはそんなに重要な話ではないと考えています。端的に言うと、仕事、友人、恋人(親子)としっかりと向き合うべきだという話です。(本の中でも割と曖昧に書かれていた)
一つ大事なことは、他者を敵ではなく、味方だと見なすことです。
そしてアドラーは、さまざまな口実を設けて人生のタスクを回避しようとする事態を指して、「人生の嘘」と呼びました。

人生のタスクに向き合うことが大切なんですね。
第三夜 課題の分離と嫌われる勇気
承認欲求を否定する
大前提として、私たちは他者の期待を満たすために生きているわけではない、というのがアドラーの考えです。
そして、それは裏を返せば、他者もあなたの期待を満たすために生きているのではない、ということになります。相手が自分の思うように動かなくても、怒ったり、妬んだりしてはいけないのです。
ここで、僕の印象に残った文章を引用します。
哲人 「ユダヤ教の教えに、こんな言葉があります。”自分が自分のために自分の人生を生きていないのであれば、いったい誰が自分のために生きてくれるだろうか”と。
『嫌われる勇気』p135 岸見一郎、古賀史健
他人の人生を生きるのではなく、自分の人生を生きることが大切だということですね。
では、承認欲求を抱かないためには具体的にどうすればいいのか。そこで、課題の分離という考え方が登場します。(個人的にここだけでも覚えれば『嫌われる勇気』を読んだ価値があります)
課題の分離
僕の実体験から例を挙げます。大学入学し、最初のテスト期間、僕は一人で勉強することが好きなのですが、友達との関係を邪険にしたくないため、複数人で集まって勉強をしていました。今帰ったら空気読めないやつとか思われてしまうんではないだろうかと思い、帰れずにいたわけです。

帰りたいけど、気まずいな…
ここで課題の分離の出番です。課題の分離とは、端的に言うと自分の課題と他人の課題を分けて考え、他人の課題には一切干渉せず、自分の課題にも一切干渉させないということです。
今回の例でいうと、僕は家で勉強する方が向いているので家に帰り、それについてみんながどう思うかは他人の課題であるから関係ない。ということになります。
この時の自分が課題の分離を知っていれば、そそくさと家に帰っていたでしょう。
もう一つ例を挙げます。自分は毎年誕生日プレゼントを渡しているのに、友達は自分にくれない。そんな友達にイラついてしまうことがあるかもしれまん。この場合、友達が僕にプレゼントを渡すかどうかは友達の課題であり、干渉するべきではないのです。私たちは見返りを求めてもいけないし、そこに縛られてはいけないのです。
余談ですが、僕は課題の分離を知った時、村上春樹さんの小説を思い浮かべました。村上春樹さんの小説にはよく、それは~~の問題であって僕の問題ではない、という文章が出てくるのです。なので、僕は課題の分離のことを問題の分離と勝手に呼んでいます。
さて、課題の分離をもう少し突き詰めて考えてみましょう。
あなたが自分の人生を自分のために生きようと決心したとき、それについてよく思わない人も必ずいるでしょう。もっというと、あなたの行動により、あなたのことを嫌いになる人がいるかもしれません。
そこで、課題の分離を行います。「自分の人生を自分のために生きる」のは、自分の課題であり、「それについてどう思うのか」は他者の課題です。たとえ他者に猛烈に批判されたり嫌われても、自分の生き方を貫くべきなのです。すなわち、嫌われる勇気を持つことが大切なのです。
哲人はこういいます。
哲人 「他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを恐れず、承認されないかもしれないというコストを支払わないかぎり、自分の生き方を貫くことはできない。つまり、自由になれないのです。」
『嫌われる勇気』p163 岸見一郎、古賀史健
第四夜 世界の中心はどこにあるか
第三夜では、対人関係をシンプルなものに変える方法として課題の分離という考えが出てきました。しかし、課題の分離をしただけで人は幸せになれるのでしょうか?他人に干渉しないというのは、一見自己中心的のようにも思えます。そこで、第四夜では、課題の分離の行きつく先である、共同体感覚についての話が出てきます。
共同体感覚という概念を理解する
アドラーの提唱する共同体感覚は、次のような定義です。
他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられること。
家族、学校、会社はもちろん、過去から未来、そして宇宙全体を含んだすべてが共同体である。
つまり、この世のすべてが自分の仲間だと見なすことを共同体感覚といいます。
より大きな共同体の声を聴け
なぜ、共同体感覚が大事なのでしょうか?
私たちは課題の分離をしていたとしても、どうしても対人関係に困ってしまうことがあります。そんなとき、共同体感覚を持っていれば、対人関係に悩むことがなくなります。
例えば、何らかの理由で学校が嫌いになり、もう学校に行きたくないと思っている人もいるでしょう。そんなときにより小さな共同体、例えば家庭などに目を向けてしまうと、引きこもったり家庭内暴力に走ってしまうかもしれない。そこで、より大きな共同体があるということを知っていれば、少なくとも殻に閉じこもって悩み続ける必要はなくなります。より大きな共同体の声を聴けという原則をぜひ覚えてください。
ちなみに哲人はこのことを”コップの中の嵐”と表現していました。ひとたび外へ出てしまえばそよ風に変わると。確かにその通りかもしれません。
縦の関係から横の関係へ
では、課題の分離から、どのようにして共同体感覚を得ることができるのか。その道筋について解説します。
それはずばり、縦の関係を横の関係に変えるのです。
縦の関係とは、他人を評価し、優劣をつける考え方に基づく関係のことです。
それに対して横の関係とは、他者を評価せず、対等であると見なす考え方に基づく関係のことをいいます。
子供が親の家事を手伝ったとして、ここで「偉いね」などと褒めることは他人を評価していることになり縦の関係だということになります。「ありがとう」など感謝の言葉を使うことで、横の関係を構築していくことができます。
さらに、感謝をする対象は、相手の行為だけではなく、存在レベルで感謝することが重要だとアドラーは言います。
しかし、横の関係を構築することや、存在レベルで相手に感謝するなど、実際に我々にできるのでしょうか…?
それについてアドラーはこう語っています。
誰かが始めなければならない。他の人が協力的でないとしても、それはあなたには関係ない。あなたが始めるべきだ。他の人が協力的であるかどうかなど考えることなく。
『嫌われる勇気』p212 岸見一郎、古賀史健
第五夜 「いま、ここ」を真剣に生きる
「自己への執着」を「他者への関心」へ
では、自己への執着を他者への関心に切り替えるためにはどうすればいいのか。それは、次の三つを行うことで共同体感覚を得ることで成しえます。
- 自己受容
- 他者信頼
- 他者貢献
自己受容とは、ありのままの自分を受け入れることです。具体的には、容姿や生い立ちなどの「変えられないもの」を受け入れ、ライフスタイルなどの「変えられるもの」は変えていく”勇気”を持つことです。
次は他者信頼についてです。他者信頼について説明する前にまず、信用と信頼の違いについて説明します。
信用:銀行の担保などのように、条件付きで信じること。
信頼:一切の条件を付けずに、無条件に信じること。
恋人が浮気しているかもしれないなどという懐疑を抱いてはいけないのです。浮気しているかしていないかは恋人の課題であって、あなたの課題ではない。あなたはただ彼女を信頼することに重きを置けばいいのです。
信頼して裏切られたらどうすればいいんだ!と思うかもしれませんが、もうお分かりですよね。裏切るか裏切らないかは相手の課題であり、自分の課題ではない。それなら信頼してしまった方が良いというわけです。それでも裏切られることがあるかもしれません。その時はその時で思いっきり悲しめばいいと、哲人は言っています。
そして他者貢献とは、大体そのままの意味で、仲間である他者に対して何らかの形で貢献をすることです。
人は、「私は誰かの役に立っている」と思えた時にだけ、自らの価値を実感することができます。つまり他者貢献とは、「私の価値」を実感するためにこそなされるものなのです。
そして、アドラーは、”幸福とは、貢献感である“といっています。
他者貢献をすることによって人は幸福になれるというのです。
そしてこの場合の他者貢献とは、目に見えないものでも構わない。貢献感を持つ、というのは私の課題であり、かつ主観です。
つまり、人は今この瞬間から幸せになることができるのです。
人生とは連続する刹那である
最後に青年が哲人にこう反論しました。
青年 「確かにわたしは他者貢献によって自分には価値があるのだと思えるかもしれない。でも、それだけで人は幸福なのですか? この世に生を受けたからには、なにか後世に名を残すような大事業を成し遂げたり、わたしが”他の誰でもないわたし”であることを証明しないことには、本当の幸福は得られないでしょう。
先生は何でも対人関係の中に閉じ込めてしまって、自己実現的な幸福について何も語ろうとされない! わたしにいわせれば、それは逃げです!」
『嫌われる勇気』p256 岸見一郎、古賀史健
他者貢献により幸福になれると哲人は言いましたが、高邁なる何かを成し遂げないことには人は本当に幸福とは言えないのではないか、というのが青年の主張です。
それに対してアドラーは、普通であることの勇気を持つことが大切だと言います。普通であることは無能であることではないのです。
さらに、人生を線としてとらえるのではなく、点として捉えることが今を生きる上では重要です。スポットライトが当てられている状態を想像してください。そこでダンスをするように生きるです。人生とは連続する刹那であり、ふと気づいて周りを見てみたら、こんなところまで来ていたのか、と思えるように生きるのです。
哲人はこういいます。
人生における最大の嘘、それは、「いま、ここ」を生きないことである、と。
最後に
ここまで読んだみなさんなら、嫌われる勇気の概略が掴めたのではないでしょうか?
課題の分離や、共同体感覚など、一筋縄では理解できない概念もあったと思います。
私自身、『嫌われる勇気』を何度も読み、その上で現実で課題の分離などを行い、分からないことがあったらまた読む、ということを繰り返しています。
もし、このブログを読んで『嫌われる勇気』に興味を持ってくれたなら、ぜひ購入してみてください。きっと世界がシンプルになると思います。

最後まで読んでくれてありがとう!